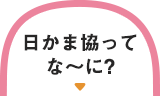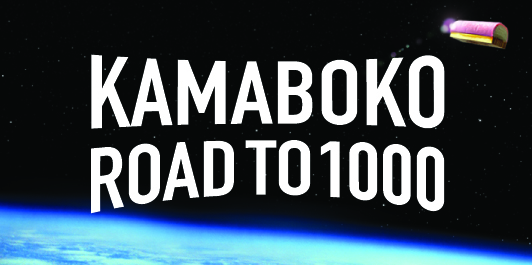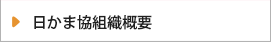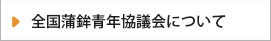ひとつの技術開発が、ある産業全体を根こそぎ変える、このような事例は前世紀イギリスで起った「産業革命」をまつまでもありません。当業界も戦後、いくつかの技術革新を至て、規模、内容ともに一変しました。以下にその足跡を辿ってみました。因みに、技術革新は現在もなお進行中です。二十一世紀を迎えて、この産業がさらにどんな変容を遂げるか、みなさんと一緒に考えてみましょう。
■魚肉ソーセージの登場:斜陽産業と呼ばれた時代

昭和29年から水産庁はマグロ漁業の拡大政策を実施します。漁船を大型化することで行動 半径は急速に拡大、その結果、生産量はそれ以後の数年間で倍増しました。そこで問題が起ります。今のように凍結施設をもたない漁船は、獲ったマグロを氷蔵していましたから、半月、二十日に及ぶ航海ののち国内に持ち帰る頃には、かなり鮮度が落ちていました。市場に揚げてもなかなかよい値段がつかない。昭和29年3月のビキニの水爆実験直後など、築地市場では一貫目(3.75キロ)100円を下回る安値を記録しました。
売れない、売れても安い。どうしたものか-と考えた末に、魚肉を使ったハム・ソーセージはどうかということになりました。この新製品は市場で爆発的な人気を博しました。ケーシングに詰めて加熱殺菌するので日保ちがよい。製法はかまぼこと同じですが、豚脂で固め、スパイスで風味をつけていましたから、その頃の消費者の“洋風好み”にぴったり。その上、量産が出来ますから価格も安い。生産量は昭和35年を境にして、急上昇、あっという間に10万トンを超え、15万トン台に迫る勢いでした。
かまぼこ類はこの新製品に食われ出し、生産活動は停滞しました。そして、この時期、わが業界は“斜陽産業“ と呼ばれる冬の時代を迎えるのです。最盛時、魚肉ハムソーセージメーカ一は200社を数えましたが、そのうち150社は、かまぼこ業者でした。
魚肉ハムソーセージの調整は意外に早く来ました。保存手段が整備されるに伴い、原料マグロが値上がりし、刺身需要が急激に増えたからです。 この時代を通じて、わたしたちは多くのことを学びました。例えば量産への可能性、日保ちの向上、そして広域流通への方法論などですが、それが緒につくまでにはなお数年を要しました。
■冷凍すり身技術の開発:包装かまぼこの登場

昭和34年に北海道水産試験場の技師、西谷喬助氏がスケソウダラの冷凍すり身化技術開発に成功しました。これが、どれほどかまぼこ業界に革命的な影響を与えたかは、それから13年後の昭和48年に、「百万トン産業」 と呼ばれるに至った経緯をみれば理解できるでしょう。
常識としては、冷凍のスケソウダラはかまぼこ類の原料にならないとされていました。鮮度低下が早い上に、冷凍によるたん白変性がさけられないためです。西谷氏とそのグループは、その欠点をすり身に砂糖と重合リン酸塩を加えることによってカバーすることに成功しました。
スケソウダラは多獲性の白身魚で、本質的にはかまぼこの原料としての適性をもつのですが、なぜか、一部の地域を除いて使われていませんでした。当時、北海道周辺でのスケソウダラの水揚げ量は年間30万トン。資源量にくらべて少なかったのですが、理由は需要が少なかったからです。漁期は冬場の抱卵期に集中して行われ、タラ子をとったあとのガラ(魚体)は食用に向けられませんでした。戦前から需要の多かったスキ身ダラの消費も低迷していました。漁業者としては誠に困った状態だったわけです。
西谷氏が冷凍すり身の開発に手を染めた動機も、スケソウダラの利用範囲の拡大とそれによる漁業振興だったのです。
陸上すり身の企業化は昭和35年に稚内で始められ、その後、道東の各基地へと拡がって行き、昭和40年代に飛躍します。当時、以西の原料事情は逼迫、近海の資源、サメ類の水揚げも減少、そういう状態のなかでこのスケソウ冷凍すり身技術の出現が、いかに大きな役割りを果たしたかは想像を絶するものがあります。計画生産が可能になり、それに適応した機械の開発も同時進行の形で行われました。
量産化を可能としたもうひとつの技術に、新潟の竹中氏ら県内業者の研究による成果「リテーナ成形かまぼこ」があります。これには包装用のフィルムの開発が当然ながら、密接に関連するのですが、これによって量産化、そしてかまぼこ業界は地元消費を中心とした地場産業という往時の伝統的スタイルから脱し広域流通食品として成長していったのです。
ケーシング詰めかまぼこは昭和47年に、リテーナ成形かまぼこは49年に、それぞれJAS規格製品に指定されました。もちろん、このような状況を完成させるためには、種々の研究開発が付随して行われたことはいうまでもありません。昭和40年代はかまぼこ業界にとってまさに技術革新の時代そのものといっても過言ではありません。この時期、本会では蒲鉾研究所を設立しました。
■カニ風味かまぼこ出現:その技術革新的意義を問う

いわゆるカニかまが市場に登場するのは昭和40年代の末からです。最初の製品は一見カニでしたが、食べてみるとかまぼこそのものでした。色をつけ、香料を入れた程度のものでした。昭和50年 代に入ると、まず“刻み”タイプが、ついで、風味、食感、ともに本物のカニと見紛うような “センイ状”の製品が登場します。
消費者は食べたいが高くて手が出ない、このような状況のなかで、イミテーションとはいえ、限りなく本物に近く、しかも値段が安い、カニ風味かまぼこが消費者の目にとまったのは当然の成り行きでしょう。昭和50年に1万トン程度だった生産量は、あっという間に2万トン台にのせます。いわゆる食品業界の新製品ラッシュのなかで、これほど消費者の人気を得た食品は、わが業界ではかつてなかったことです。これを契機に、業界には凄まじい新製品開発の胎動が始まるのですが、それはもう少しあとのことです。
スタートダッシュは力強かったものの、カニかまの生産量は、その後しばらく1~2万トン台で上下することになります。しかし、その安定帯をつき破ったのが海外、特に米国での需要の高まりです。外国への輸出が始まったのは昭和50年代の前半からですが、56、57年を契機に急上昇、これに伴って生産量は急カーブを描きました。59年に7万トン台にのせ、61年には7万3千トンと最高を記録しますが、これ以後ペースダウンします。
主要輸出国だった米国内での生産が始まり、しかも、年とともに増加していったからです。わが国のメーカーも、これに対応して、輸出から現地生産に切りかえます。昭和63年の生産量は6万トンぎりぎりまで落ちています。国内の需要は頭打ち、対米輸出も採算的に難しいということで、これからの見通しとしては、国内生産量は微減、輸出は米国以外、特にヨーロッパ方面にシフトせざるを得ないでしょう。
しかし、この新製品のもたらした業界への影響は決して小さなものではありません。在来型の製品と全く異質のかまぼこの市場性が、技術革新によって生れたこと、そして日本の伝統的魚肉加工技術から生れた製品が世界に通用することを立証したことです。
ただ、この貴重な技術革新の結果が、諸般の事情によって特許を得ることがないまま世界に公開されてしまった事実は、いま思い返すと惜しい限りです。
日本のかまぼこから世界のかまぼこへ。新しいタイプのかまぼこ、つまり、珍味かまぼこ時代への端緒となったこと、それに即応して技術の高度化が進められたこと、これは画期的なことではないでしょうか。